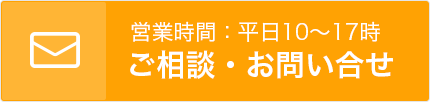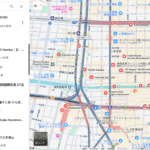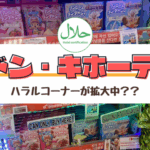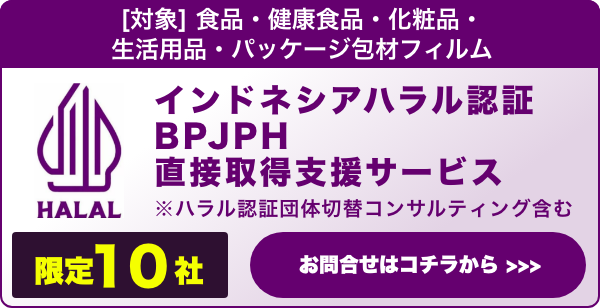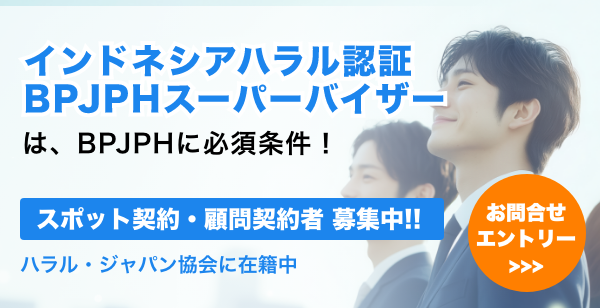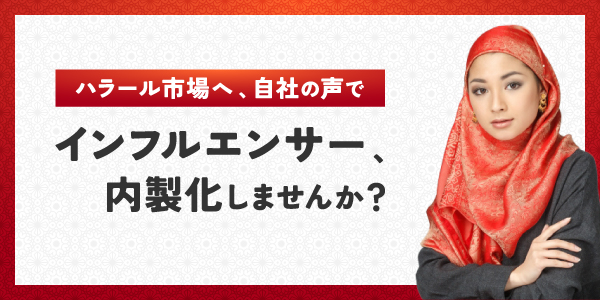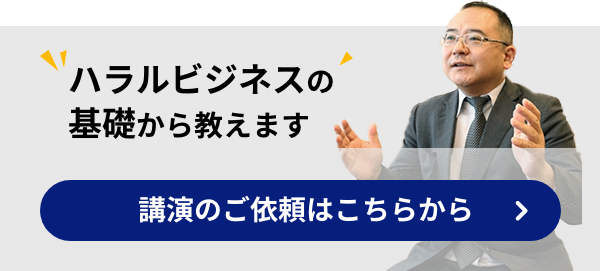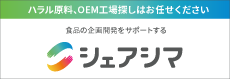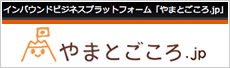「台湾ムスリム」はどこから来て、どう暮らしているのか? 台北モスクから見た“現地の今” (台湾レポート4/4)
2025年6月、台湾出張の一環として、台北最大のモスク「台北グランドモスク」を訪問しました。今回は、同モスクで指導を務めるイマーム(イスラム指導者)の方など現地ムスリムの方々にインタビューする機会を得て、台湾のムスリム社会の実像に触れることができました。


台北グランドモスクは、1960年にバイ・チョンシー氏の尽力で設立された台湾最大のイスラム教礼拝施設です。礼拝の場であるだけでなく、宗教・文化交流の場としても活発に活用されています。
たとえば、
- ・改宗者向けの入門セミナー
- ・アラビア語やイスラムの歴史を学べる教室
- ・書道など台湾文化との交流イベント
など、信仰と地域文化を“橋渡し”する役割を担っています。
また、ラマダン明けのイード(断食明けの祝祭)には、台北市政府と連携してモスク隣の広場で大規模なイベントも開催。行政との協働からも、台湾社会におけるムスリムの存在感の高まりを感じさせます。
台湾のムスリム人口は決して多くはありませんが、その構成は実に多様です。モスクで聞いた主な出身背景は、以下の4つに分類されます。
- 1. 中国大陸のムスリム地域(回族など)からの移住者
- 2. インドネシア・マレーシアなど東南アジアからの労働者・留学生
- 3. 改宗した台湾人(増加傾向)
- 4. その他イスラム諸国出身者(中東、南アジアなど)
中でも注目すべきは3の「改宗ムスリム」の存在です。
最近では週に1人以上のペースでシャハーダ(信仰告白)を行う改宗者が現れているといい、20〜40代の若い台湾人が中心とのこと。うち1割程度は外国籍の非ムスリムからの改宗という例もあり、国際的な文化接触や精神的価値観の転換が背景にあると見られています。
特に、英語が堪能な層が多く、イスラムとの知的接触の間口が広がっているという点も、台湾独自のムスリム社会の特色です。
モスクで暮らすムスリムたちにとって、台湾はどう映っているのか?
インタビューでは、以下のような現地での生活実感が共有されました。
ポジティブな点:
- ・宗教的寛容さが社会に根付いている。
例)徴兵中にお祈りの時間の確保をお願いしたところ、指導官が快く配慮してくれた。
- 行政との協力が進んでいる(モスクの運営支援、公共イベントへの協力など)
課題・困難な点:
- ・台湾ローカル料理の多くが非ハラルで選択肢が限られる。
※一方で「素食(ベジタリアン料理)」文化があり、代替手段も模索可能。
- ・ネット上には一定の偏見的書き込みが存在しており、表面的な寛容さと本音のギャップに戸惑うことも。
こうした課題に対し、モスクとしては正確な情報発信を通じて理解を深める努力を継続していきたいとのことでした。


今回の訪問で印象的だったのは、「観光客としてのムスリム」ではなく、生活者・社会構成員としてのムスリムにしっかり焦点が当たっていることでした。
日本でも今後、ムスリム観光客だけでなく、労働者・学生・生活者としてのイスラム教徒が増えていく可能性があります。
異文化交流や食の多様性を考える時、今、そしてこれから、私たちは何をすべきなのか。台湾のムスリム社会は、1つの実践例といえるでしょう。
ハラル・ジャパン協会では、認証だけでなく、インバウンド向けイスラム対応や外国人人材活用まで幅広く支援しています。ご関心のある方は、ぜひハラル・ジャパン協会までご相談ください。
文責
ハラル・ジャパン協会
ハラルビジネスコンサルタント 田上明日菜