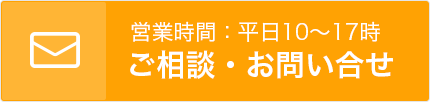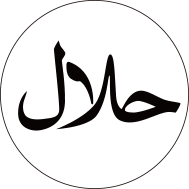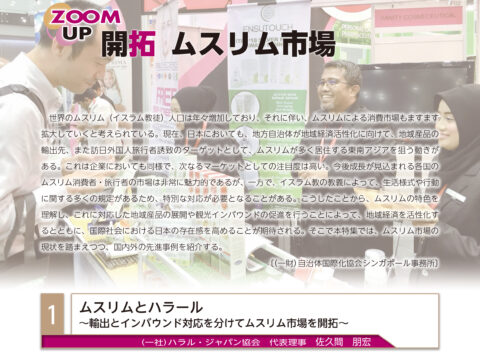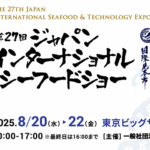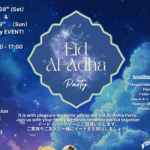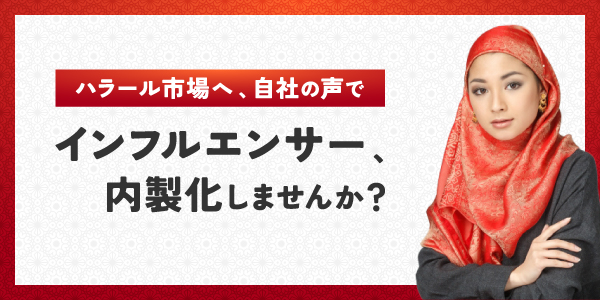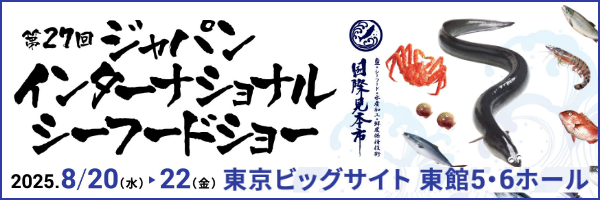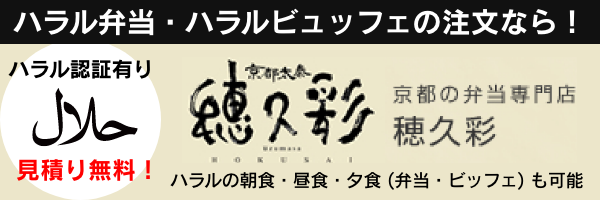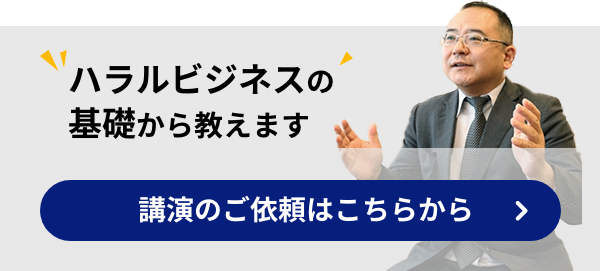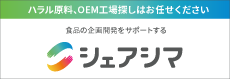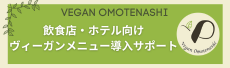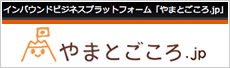ハラル認証はマレーシアのJAKIMから着手すべし
インドネシアのハラル認証BPJPHではなく、まずはマレーシアのハラル認証JAKIMから着手すべし
ハラル認証はマレーシアからインドネシアへ移行!?
まずはマレーシアのハラル認証JAKIMスタイルをきちんと学ん
特にインドネシアのハラル認証のワナに要注意です。
海外ハラル認証市場では、
LPPOM-
すでにハラル認証を取得している企業は、新たにBPJPHハラル認証を再取得しなけ
コロナ禍における国内企業のハラル認証取得については、部外者の工場立入制限などで
上記のインドネシアのハラル制度変更を受け、すでに輸出している健康食品・
また、タイ・ベトナム・フィリピンはイスラム教国ではありませんが、
こうした状況を踏まえ自社がハラルビジネスを活用してイスラム市場に取り組むか、または取り組まないかの「経営判断」をするためにも最新のハラル認証を再度学習しなおす必要があります。
日本企業としては、HACCP、ISO、
ハラル・ジャパン協会ではハラル認証業界の動向や最新の情報をいち早く入手し、企業に有利な戦略をご提案させていただきます。ハラル認証団体ではないので、本当にハラル認証が必要かどうかの判断をはじめ取得のサポートでは、各認証団体の特色や実績を徹底比較し中立的な立場で選定に有利な情報とアドバイスを提供することができます。ハラルに関することは当協会に是非相談ください。